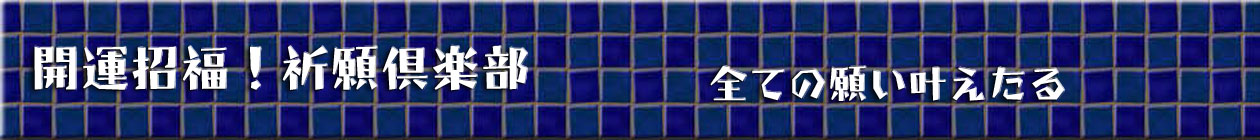キリスト教には、先祖供養という考え方がありません。
先祖を敬うことはしますが、拝むようなことはないのです。
キリスト教では、神様はキリストのみです。
崇拝してしまえば、亡くなった人が神格化してしまいます。
それはキリスト教のような一神教では許されないのです。
お墓参りという行為も存在しますが、決して重要視はされません。
亡くなった人は神の元で安らかに暮らしている、と考えられています。
そのため、お墓参りでは故人に思いを馳せ、神様に感謝の気持ちを捧げるのです。
また、お墓や亡骸も重視されていません。 続きを読む キリスト教の先祖供養