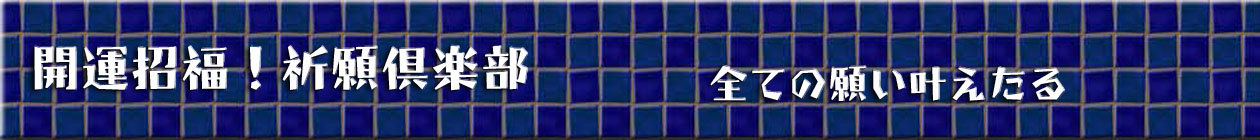戦国時代の武将でもっとも合戦の勝ち数を上げているのは豊臣秀吉ですが、じつは勝率でもトップを取っています。
戦歴84勝8敗7分けですから、8割5分2厘という好成績。
とくに信長なき後は朝鮮出兵まで負け知らずの連勝を続け、その中には北条氏を追放した小田原征伐も含まれています。
大量の物資と人材を投入、相手を威圧して勝つ戦法は「戦わずして勝つ」と明言を残し、水攻めや兵糧攻めによる戦法こそ秀吉の真骨頂と取られがちですが、「戦わずして勝つ」以前はむしろ、激戦の最中、火中の栗を拾うがごとく、危険で勝利の確率が低い合戦に進んで身を投じていました。
その代表的な例が金ケ崎の戦いでしょう。 続きを読む 火中の栗を拾った木下藤吉郎