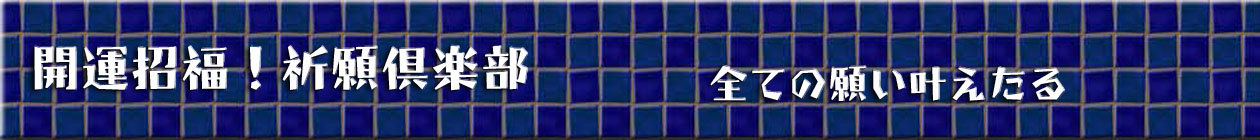七福神に名を連ねている大黒天はふたつの俵の上に乗り、大きな袋を抱えて打ち出の小槌を握っているという、いかにも商売繁盛の神様に相応しい容姿をしていますが、出身がインドのヒンドゥー教で、しかも戦闘と財福と冥府の神様だっただけに大黒天だけを本尊としている神社はあまり多くありません。
神仏分離によって大黒天を祀っていた神社は大黒天が習合した大国主命を祀り、大黒天は寺院に祀られているケースが目立ちます。
日本で最初に大黒天を祀ったといわれているのが大阪は曳野市、町名も大黒という大黒寺。 続きを読む 大国主命と習合した大黒天