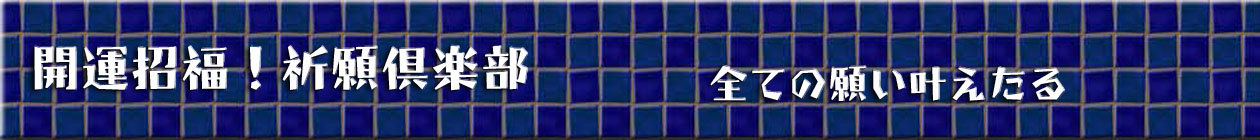日本の伝統的な縁起物で知られるだるま、選挙でもおなじみですが、だるまを購入する時は目に墨の入っていない状態で渡されます。
この墨、どうやって入れるのかというと、もっとも一般的なのは祈願することを思いながら向かって右、だるまの左目から入れて開眼させ、祈願成就したあかつきには向かって左、右目に墨を入れるとのこと。
左目が先の理由は陰陽五行が根本にあり、だるま本体の赤は厄除けの意味を持つ火で南を表し、物事の始まりは東から生まれ、西で消滅するといわれていることから、だるまを南に向けると左目が東に向くので、左目から墨を入れるそうです。 続きを読む だるまの目の入れ方