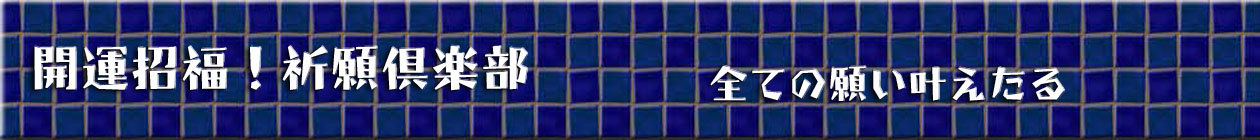言霊の実用例はスポーツの世界で顕著に表れています。
もっとも分かりやすいのは1960年代後半から1970年代前半までヘビー級ボクサーとして活躍したモハメド・アリことカシアス・クレイ。
1964年にヘビー級王座獲得後にイスラム運動組織に加盟していたことからモハメド・アリと改名しましたが、このボクサー、じつに口が達者な上、対戦相手を罵倒することで有名でした。
蝶のように舞い蜂のように刺すと自らのボクシングを美化、三度対戦した宿敵のジョー・フレイジャーには悪態の吐き放題。 続きを読む 勝つことへの強い意思が現れたアリの言霊